問題
「大型一種免許で回送のため大型バスを運転した。」
答え
⭕️(正しい)
解説
道路交通法における免許区分では、大型一種免許があれば大型バス自体を運転することは可能です。
ただし注意点があります。
- 大型二種免許が必要なのは「旅客輸送を目的とした運転」
- **回送(お客を乗せずに車両を移動するだけ)**であれば、大型一種免許で運転できる
つまり「運転そのもの」に必要なのは大型一種、「旅客輸送業務」に必要なのが大型二種、という関係です。
大二種免許とは

大型二種免許は、バスやタクシーなど旅客を有償で運送する業務に従事する際に必要な免許です。
- 路線バス、観光バス、高速バス、貸切バスなど
- タクシー、ハイヤー
- 送迎バス(幼稚園・病院など)
これらは「人を運ぶ」ことが目的なので、一種免許では不可、必ず二種免許が必要です。
旅客輸送とは
「旅客輸送」とは、乗客を輸送することを目的として自動車を運行することをいいます。
- 有償運送(お金を受け取って客を乗せる)
- 無償でも、旅客を定常的に運ぶ業務
👉 一方で「回送」「回収」「整備のための移動」は 旅客輸送に該当しません。
したがって、大型一種免許保持者でも運転可能です。
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の乗車人数制限
旅客輸送かどうかにかかわらず、それぞれの免許には 運転できる車の種類・定員・車両総重量に制限があります。
- 普通免許
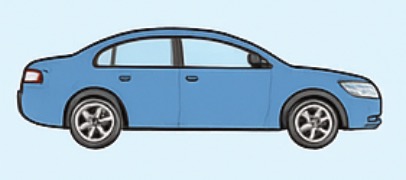
- 車両総重量 3.5t未満
- 最大積載量 2t未満
- 乗車定員 10人以下
- 準中型免許

- 車両総重量 7.5t未満(※限定解除で10t未満まで)
- 最大積載量 4.5t未満
- 乗車定員 10人以下
- 中型免許

- 車両総重量 11t未満
- 最大積載量 6.5t未満
- 乗車定員 29人以下
- 大型免許

- 上記を超えるすべての車両
- 大型バス(定員30人以上)も運転可能
👉 よって「大型バスを走らせる」だけなら大型一種で可能。ただし「お客を乗せる」なら大型二種が必要です。
大型バス運転時の注意点
大型バスは、普通車と比べて操作特性が大きく異なります。
車両感覚(幅・長さ)
- 車幅は2.5m前後、全長は12m近い場合もあり、普通車の約2倍。
- 車線変更や左折・右折では、十分な余裕を取らないと接触の危険があります。
死角の多さ
- 運転席が高いため、直前や側方に広い死角が存在。
- 特に右左折時の歩行者や自転車の巻き込みに注意。
前車輪の位置
- 大型バスは運転席より後ろに前車輪があります。
- 内輪差が大きくなるため、曲がるときに思った以上に後輪が膨らむ。
エアーブレーキの特徴
- 普通車の油圧式と違い、空気圧を利用。
- 反応がワンテンポ遅れるため、踏み加減が独特。
- 強く踏みすぎると急ブレーキに、弱いと効かないこともある。
排気ブレーキの活用
- 下り坂ではフットブレーキだけに頼らず、排気ブレーキを使用。
- 長い下り坂ではエンジンブレーキと併用し、フェード現象を防ぐ。
旅客輸送を想定した運転
- 実際に人を乗せる場合は「加速・減速をできるだけ滑らかに」が鉄則。
- 回送中も同じ姿勢で運転する習慣が、安全運転につながる。
まとめ
- 大型一種免許で大型バスを「回送」することは可能。
- 「旅客輸送」を目的とする場合は大型二種免許が必須。
- 普通・準中型・中型・大型免許にはそれぞれ定員・重量制限がある。
- 大型バスは車両感覚やブレーキ特性が普通車と大きく異なるため注意。
👉 学科試験では「一種で回送は⭕️」「旅客輸送は二種必須」という区別をしっかり押さえるのがポイントです。



