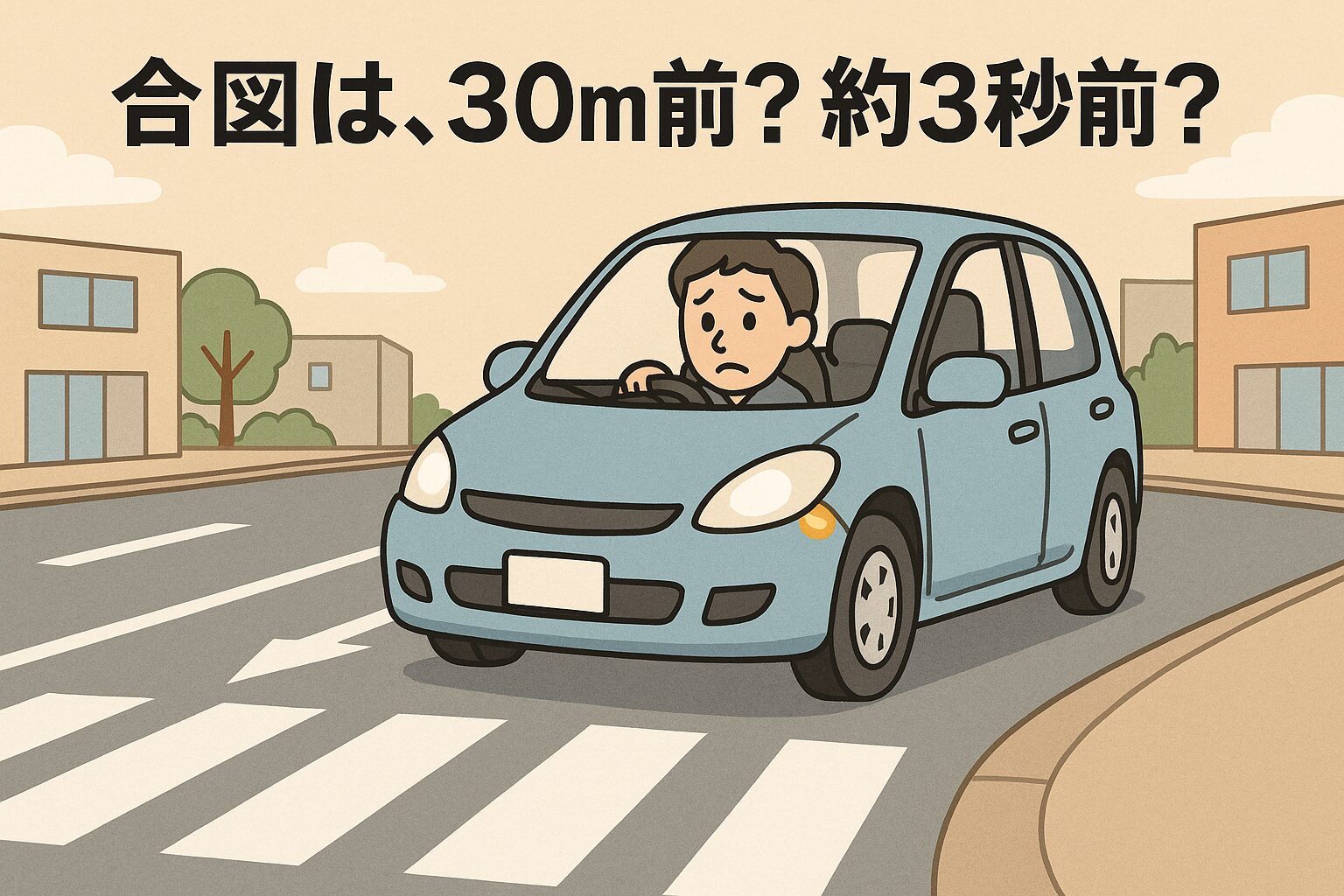はじめに
「合図は30メートル前に出す」
「いやいや、3秒前が正解でしょ?」
――自動車学校で学んでいると、こんなやりとりを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、これらはどちらも正解。ただし 状況によって適用される場面が違う のです。
学科試験では、この違いを正しく理解していないと「引っかけ問題」に見事にひっかかってしまいます。
そこで今回は、「30m前」なのか「3秒前」なのか をしっかり整理し、さらに検定や実際の運転で役立つ感覚的な捉え方も交えて解説します。
問題
「右左折や進路変更の合図は、行為を始める30m前までに出さなければならない。」
答え
👉 ×(誤り)
理由(法律上の規定)
道路交通法施行令 第21条では、合図の時期について以下のように規定されています。
- 右左折・転回・横断
→ 行為を始める 30メートル手前 - 進路変更
→ 行為を始める 約3秒前
つまり「右左折も進路変更も全部30m前」という理解は誤り。
右左折や転回は距離で、進路変更は時間で と覚える必要があります。
なぜ「30m」と「約3秒」で分かれているのか?
一見ややこしく思えるこの区分ですが、実は合理的な理由があります。
■ 右左折・転回・横断 → 30m前
交差点で右折・左折をするときは、必ず 徐行の義務 があります。
速度がある程度決まっているため、「30m」という具体的な距離で指示した方が運転者にとって理解しやすいのです。
■ 進路変更 → 約3秒前
一方で進路変更は、速度によって適切な距離が大きく変わります。
高速道路を走行中に「30m前」と決めてしまうと、ほんの0.5秒前にしか合図を出せないこともあり、逆に危険です。
例えば、30km/hで走っていれば3秒で約25m、50km/hなら約40m以上進みます。
速度ごとに距離を決めるのは複雑で現実的ではありません。
そこで進路変更については、「どの速度でも通用する感覚的な基準」として 約3秒前 という時間が採用されています。
技能検定でのポイント
● 右左折の合図
- 交差点30m手前での合図は鉄則。
- 遅れた場合:交差点直前での合図は減点対象。
- 早すぎる場合:所内検定では特別減点(2回目以降から適用)、路上検定では減点対象。
● 進路変更の合図
- 「余裕をもって約3秒前」が求められます。
- 車線変更を始めてから合図を出すのは論外。
30mを体感するコツ
「30mってどのくらい?」と聞かれて即答できる人は少ないでしょう。
実際の教習では、以下のように感覚を掴むと良いです。
- 所内コースの場合
→ 次に曲がる交差点の「ひとつ手前の大きな交差点(クランクやS字の出入口などを除く。)」に差し掛かったタイミングで合図を出すと、だいたい30m前に近い。 - 路上コースの場合
→ 電信柱の間隔は一般的に 30〜50m程度。電信柱1本分を目安にすると「これくらいの距離感か」と掴みやすい。
3秒前を体感するコツ
進路変更の「約3秒前」は、距離で捉えられないため、感覚的な訓練が必要です。
- 「心の中で『ゼロいち、ゼロに、ゼロさん』と数える」
→ 「ゼロ」を入れることでテンポが安定し、余裕を持った3秒を確保しやすい。 - 思っているよりもやや早めにウインカーを出す
- 「合図を出してから確認」ではなく、「確認してから合図」でリズムを作る
👉 つまり「約」という曖昧さを逆手にとり、早めを心がけるのがコツです。
学科試験での落とし穴
学科試験では、このテーマは以下のように出題されることがあります。
- 「右左折や進路変更の合図は、行為を始める約3秒前までに行う」 → ×
- 「進路変更の合図は、行為を始める約3秒前に行う」 → ○
- 「右左折や転回の合図は、行為を始める30メートル手前で行う」 → ○
ほんの一言の違いで正誤が逆転します。
**「30m=曲がるとき」「3秒=進路変更」**とワンセットで覚えましょう。
まとめ
- 右左折・転回・横断 → 30m前
- 進路変更 → 約3秒前
- 技能検定では「合図の遅れ」は即減点対象
- 感覚のコツ:
- 30m=電信柱1本分/所内は交差点ひとつ手前
- 3秒=『ゼロいち、ゼロに、ゼロさん』と数える
学科試験でも、実際の路上運転でもよく問われるのがこの「合図のタイミング」。
「3秒と30m」を正しく理解しておくことが、安全運転にも合格への近道にもなります。