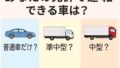「あなたの持っている免許で何が運転できますか?」
この問いに、すぐ答えられる人はどれくらいいるでしょうか。
「私は普通自動車免許を持ってます。」
そう答えたとして、その普通免許で次のクルマは運転できるでしょうか?
- 最大積載量4トンの貨物自動車
- 最大積載量2トンのトラック
- 最大積載量1.5トンの小型貨物
正確に答えられる方は意外と少ないのです。なぜなら、免許を取得した年代によって、運転できる車の範囲が大きく異なるからです。気づかないうちに「本当は運転できない車」を運転してしまい、無免許運転で処罰されるケースすらあるのです。
そこで今回は、免許制度の歴史をひも解きながら「あなたの免許でどんな車が運転できるのか」について解説していきます。
1、最大積載量と車両総重量を理解する
まず、免許制度の違いを理解するには「最大積載量」と「車両総重量」の違いを押さえることが重要です。
最大積載量とは?
最大積載量とは、その車に積める荷物の最大の重さのことです。
※車両自体の重さは含まれません。

例えば「4トン車」という表現を耳にしますが、この「4トン」とは「最大積載量4トンの貨物自動車」という意味です。つまり「トラックの重さが4トン」ではなく「荷物を4トンまで積めるトラック」ということ。ここを誤解している方が実はとても多いのです。
車両総重量とは?
一方、車両総重量とは次の合計です。
- 車両本体の重さ
- 積荷の重さ(満載の状態)
- 乗員の重さ(1人あたり55kg換算)

この総重量が免許区分に大きく関わってきます。よく「中型8トン」という表現を耳にしますが、この「8トン」とは車両総重量を意味しています。
みんながよく言葉にする「○○トン」は最大積載量のことが多い。
そして免許に記載されている「○○トン」は車両総重量のこと、、ということです。
2、免許制度の歴史
わかりやすく図で解説している記事はこちら👇
https://online-ds.jp/2025/08/29/menkyo-diagram-explanation/
2007年以前の制度
2007年以前は普通免許を取得すると、最大積載量5トン未満・車両総重量8トン未満まで運転できました。
これ以上の車両を運転するには大型免許が必要でしたが、当時は「中型免許」が存在しなかったため、大型免許を取れば一気に制限が解除されていたのです。
しかも当時の大型免許は、今の「中型車(5トン車)」で教習を受けるケースが多く、当時の普通自動車でも運転することができた4トン車よりも車自体の大きさは小さく、比較的簡単に取得できました。今では考えられない「夢のような時代」だったともいえるでしょう。
しかし、大型車両による重大事故が相次ぎ、安全性が問題視されるようになりました。そこで行政は「大型免許のハードルを上げる」ために制度を改正し、2007年に中型免許を新設しました。
2007年改正:中型免許の導入
この改正で普通免許の範囲は一気に縮小。
最大積載量5トン未満 → 3トン未満
車両総重量8トン未満 → 5トン未満
新しく誕生した中型免許では、最大積載量3トン以上6.5トン未満・車両総重量5トン以上11トン未満が対象となり、それ以上は大型免許が必要となりました。
さらに大型免許の教習はそれまで使用していた「最大積載量5トン車」から「最大積載量10トンクラスの車両」で実施されることになり、大型取得のハードルは格段に高くなったのです。
2007年改正の問題点
大型免許取得のハードルを上げるため、中型免許を新設したわけですが、ここには大きな問題点がありました。
問題点1:物流業界の人手不足
それまで18歳で普通免許を取れば、4トントラックを運転することで働くことができました。
しかし改正後新たに取得する普通自動車免許では、最大積載量4トンのトラックを運転することはできませんから、中型以上の免許が必要になります。しかし、中型免許を取得するためには「免許取得後2年以上」かつ「20歳以上」が条件であり、若者が物流業界に入っても使い物にならないと評価されるようになり、18歳(高校を卒業してすぐ)物流業界で働こうとする若者がいなくなってしまったのです。
その結果、トラック協会や全国高等学校長協会が立ち上がり、「若者が就職できる環境を戻してほしい」と行政に働きかけました。
問題点2:制度の複雑化による無免許運転
一見すると「普通免許で2トン車は運転できる」と思えます。
しかし実際には冷蔵車や高所作業車、パッカー車、クレーン車など、多くの2トン車は車両総重量が5トンを超えてしまいます。つまり普通車免許では運転することができないので、中型免許以上が必要なのです。法改正から一般的にこの事実の周知に時間を要したため、
さらに制度の複雑さから「気づかない無免許運転」が続出し、取り締まり件数も増加しました。
2017年改正:準中型免許の導入
そして、こうした制度の不備を修正する形で、2017年には準中型免許が新設されました。
普通免許の範囲はさらに縮小し、
最大積載量2トン未満・車両総重量3.5トン未満となりました。
一方、新設された準中型免許(18歳以上で取得可能)では、
最大積載量2トン以上4.5トン未満・車両総重量3.5トン以上7.5トン未満
が運転可能となり、すべての2トン車をカバーできるようになりました。
つまり「普通免許では2トン車すら運転できない」代わりに「準中型を取ればOK」という構造に変わったのです。
わかりやすく図で解説している記事はこちら👇
https://online-ds.jp/2025/08/29/menkyo-diagram-explanation/
3、教習所業界への影響
この制度改正で頭を抱えたのが、実は我が教習所業界です。
- 新しい免許区分が増えるたびに、新しい車を購入しなければならない
- 教習区分が複雑になり、間違いが起きやすい構造になった
- コースを改修し、公安委員会の基準に合わせなければならない
- 大型車両の教習は広大なコースが必要になり、実施できる教習所は減少
その結果、大型教習が現中型車で行っていた時代から、最大積載量10トンクラスで行うことになり、教習所に広大な土地が必要になったことから、大型教習を実施する教習所が少なくなったことで、大型免許をやっている教習所が少なくなるわけですから、免許も取りづらくなり、こうした背景がさらに物流業界の人手不足に拍車をかけている可能性があります。
まとめ
今回は第1章として、免許制度の歴史的な背景を整理しました。
- 普通免許で運転できる範囲は、取得年代によって大きく異なる
- 2007年・2017年の改正で普通免許の範囲は縮小され続けている
- 背景には安全性の確保や物流業界の人手不足問題がある
- 教習所業界も制度改正に大きな影響を受けている
次回の第2章では、年代ごとに「普通免許で乗れる車」を図解しながら、さらにわかりやすく解説していきます。
次の記事へ