「高齢者講習って、いつから義務になったの?」
「昔はどんなことやってたんだろう?」
こんな疑問を持ったことはありませんか? 実は高齢者講習には、時代とともに少しずつ変わってきた歴史があります。
この記事では、その流れを振り返りつつ、制度の変遷とその裏にある理由も探っていきます。
📘 年表でみる|高齢者講習の歴史と制度の変遷
| 年度 | 主な出来事 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 1980年代後半 | 高齢者講習の開始(任意) | ・教習所や警察主導で希望者対象の講習 ・制度化されていなかったが安全教育的に実施 |
| 1997年 | 75歳以上に義務化 | ・初の制度化 ・免許更新時に「高齢者講習」の受講が必須に |
| 2001年 | 対象年齢を70歳以上に引き下げ | ・内容は3時間(講義・検査・実車) ・CRT(複合反応検査)も導入 |
| 2009年 | 認知機能検査の導入 | ・75歳以上に義務化 ・記憶力・判断力などをチェック |
| 2017年 | 認知機能検査の結果により講習を分岐(講習の高度化・合理化) | ・2時間講習/3時間講習に分かれる ・違反者には臨時認知検査・技能検査も新設 |
| 2022年〜 | 全講習を2時間に統一 & 制度高度化 | ・講習および認知検査の簡素化 ・運転技能検査の強化、評価基準の見直し |
1.高齢者講習の始まり ― 希望制からのスタートとその背景
1980年代後半、日本は高齢化社会の入り口に差し掛かっていました。高齢運転者による事故が少しずつ注目され始め、「安全運転を続けてもらうための対策」が模索されるようになります。そんな中で、全国の一部地域では、**高齢ドライバーを対象にした“任意参加の講習”**が試験的にスタートしました。
この講習は、あくまで希望制。法的な義務ではなく、「受けたい方はどうぞ」という立て付けの、いわば高齢者向けの“安全運転教室”でした。内容は現在の高齢者講習に通じるもので、視力や反応速度などのチェック、運転への助言などが含まれていました。
ところで、この動きにはもう一つの背景があると言われています。
それは――少子化の影響で教習所の経営が苦しくなり始めていたこと。
1990年代を目前にして、18歳人口は減少に転じていました。若者が少なくなれば、教習所の入校者も当然減ります。そんな中、高齢者講習の委託事業は「新たな需要」として、教習所にとって大きな助けになったという側面も否定できません。
このように、高齢者講習は「高齢ドライバーの安全確保」と「教習所の経営支援」という、複数の目的が絡み合って始まった制度とも言えるでしょう。
2.1997年|75歳以上に高齢者講習が義務化
1997年、それまで任意だった高齢者講習が制度として整備され、75歳以上の運転者に対して受講が義務化されました。
この背景には、高齢ドライバーによる交通事故の増加と、今後の高齢化社会の到来に対する危機感があります。
当時、交通事故全体の件数は増加傾向にありましたが、その中でも高齢者が関与する事故の割合が年々高まっていました。特に、判断力や認知機能、動体視力の衰えなど、加齢による運転能力の低下が一因とされる事故が注目されるようになります。
さらに、1990年代に入り日本は急速に高齢化社会へと進み始めており、「これまで通りの免許更新制度では対応しきれない」といった声が上がっていた時代でもあります。
そうした社会的背景を踏まえ、国はまず75歳以上の高齢ドライバーを対象に講習の受講を義務化することで、安全運転に必要な能力の確認や意識の向上を図ることを目指しました。
この時点では、視力や聴力の検査、座学による交通ルールの確認、そして実車による運転操作のチェックなどが行われるようになり、高齢者講習の原型が形づくられたのです。
3.2001年|対象年齢が70歳以上に引き下げられる
1997年の制度改正によって、75歳以上の運転者に高齢者講習の受講が義務付けられて以降、交通事故件数や社会の高齢化を受けて、制度はさらに見直されることとなりました。
そして2001年には、講習の義務化対象年齢が「70歳以上」へと引き下げられます。
背景には、70歳を超えたあたりから運転技能や判断力、視覚機能などに変化が見られるケースが増えるという研究結果や事故統計がありました。75歳という区切りではカバーしきれないリスクを早期に把握し、対策を講じるための年齢引き下げだったと言えるでしょう。
この当時の高齢者講習は、3時間にわたる内容で、以下の3つのセクションで構成されていました。
■ 講義(1時間)
道路交通法の最新情報や、高齢ドライバーに特有の注意点、安全運転の心構えなどを学ぶ座学です。加齢による身体機能や認知機能の変化についても触れ、自身の運転を見直すきっかけになります。
■ 検査(1時間)
視力・聴力・動体視力などの基本的な身体機能に加えて、**CRT(Complex Reaction Test:複雑反応テスト)**が行われます。
CRTは、光や音などの複数の刺激に対して、どれだけ正確かつ素早く反応できるかを測定する検査で、加齢による反応遅れを客観的に確認できるツールです。
CRTには、以下のような2つの検査が含まれていました。
◆ 選択反応検査
画面に現れる歩行者の属性(例:小さな子供、大人、自転車)に応じて、
- アクセルを踏み続ける
- アクセルを離す
- アクセルを戻してブレーキを踏む
という3つの操作の中から正しい反応を素早く選択する検査です。
交通状況を瞬時に判断して適切な操作ができるかを確認します。
◆ 注意配分複数作業検査
選択反応検査を行いながら、同時に**ハンドル操作(車線の維持など)**も求められます。
これにより、**判断力と同時に複数の作業を処理する能力(いわゆるマルチタスク能力)**がどの程度保たれているかを測定します。
■ 実車指導(1時間)
教習所内のコースを実際に運転し、指導員がブレーキ操作、ハンドル操作、周囲の確認といった基本動作をチェックします。普段の癖や見落としがちな注意点を指摘してもらえる、いわば“運転の健康診断”のような時間です。
このように、高齢者講習は「知識・判断・技能」の3要素を網羅的に確認する構成となっており、単なる形式的なものではなく、安全運転の意識を高める重要な機会として位置づけられていました。
4.2009年|認知機能検査の導入
2009年、高齢ドライバーによる事故の増加を受けて、さらなる対策が講じられました。この年から、75歳以上の運転免許更新者に対して「認知機能検査」が義務化されます。
この検査は、更新手続きを行う前に受ける必要があり、運転に必要な記憶力・判断力の低下が見られるかどうかを評価することを目的としています。以下の3つの項目が実施されました。
認知機能検査の内容(2009年当時)
- 時間の見当識
年月日や曜日、時間帯などを答えることで、時間に対する認識力を測定します。 - 手がかり再生
複数のイラストや単語を記憶し、一定時間後に思い出して答える記憶力の検査です。 - 時計描画
指定された時刻のアナログ時計を描かせることで、空間認知能力や注意力をチェックします。
検査結果とその後の対応
この時点では、たとえ認知機能検査の結果が「認知症のおそれあり」と判定されても、その時点で医師の診断を受ける義務はなく、誰もが高齢者講習を受けることで免許更新が可能でした。
ただし、その後に交通事故などを起こした場合は、
- 認知機能検査で「認知症のおそれあり」とされていた方について、
- 医師の診断が義務付けられ、
- 診断結果が**「認知症」とされた場合は免許が取り消される**、
- 一方で**「認知症ではない」と診断された場合は引き続き運転が認められる**
という運用がなされていました。
このように、制度の初期段階では「予防的検査」としての意味合いが強く、検査結果だけで直ちに運転を制限されるわけではありませんでしたが、のちの制度改正につながる大きな第一歩となったのです。
5.2017年|講習の高度化・合理化と分岐化
2017年、道路交通法の改正により、高齢者講習制度が大きく見直されました。
この改正の柱となったのが、**「高齢者講習の高度化・合理化」**です。
具体的には、75歳以上の高齢ドライバーに義務付けられていた認知機能検査の結果に応じて、受講すべき講習が2時間または3時間に分かれるようになりました。これにより、ドライバーの認知機能や運転技能に応じた、より柔軟で実効性の高い講習が行えるようになったのです。
認知機能検査の結果による講習の分岐
- 記憶力・判断力に問題なし(第1分類)
→ 2時間の高齢者講習(通常講習) - 記憶力・判断力に少し低下の恐れあり(第2分類)
→ 3時間の高齢者講習(通常講習) - 認知症の恐れあり(第3分類)
→ 医師の診断が必要
→ 認知症でないと診断された場合に限り、3時間の特定高齢者講習(高度化された講習)を受講
※3時間講習では、2時間講習の内容に加え、実車指導の様子を映像で記録し、その映像を自身が客観的に確認することで、自身の運転を見つめ直すとともに、指導員から個別に指導を受ける形のものだった
臨時講習・臨時検査の導入
この改正ではさらに、以下のような制度も新設されました。
- 臨時認知機能検査
特定の違反(信号無視・通行区分違反など)をした75歳以上のドライバーに対して、更新時期に関わらず認知機能検査を実施 - 臨時高齢者講習
臨時認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定され、かつ医師の診断で「認知症ではない」とされた場合に受講が必要
これにより、高齢ドライバーの中でも特にリスクの高い層を早期に把握し、適切な教育・管理を行う体制が整えられました。
高齢化が進む中で、社会全体の交通安全を守るための大きな一歩となった改正です。
しかし、この改正が行われた頃から、いわゆる「団塊の世代」が次々と高齢者講習の対象年齢に達するようになり、全国の教習所では講習予約の飽和状態が発生するようになっていきます。
これまで高齢者講習は、指導員1名に対して受講者3名で実施するのが原則とされていましたが、この方式では急増する受講希望者に対応しきれず、「予約が取れない」「更新期限に間に合わない」といった混乱が各地で相次ぎました。
その対応策として、講習の実施人数の上限が見直され、1名の指導員で最大6名まで対応できるように制度が改正されました。
これにより、ある程度の緩和が見られたものの、現場の負担は依然として大きく、制度の運用には慎重な配慮が求められる状況が続きました。
また、この時期には事故分析も進み、「認知機能の低下」だけが高齢運転者のリスク要因ではないことが明らかになってきます。
特に、信号無視や通行区分違反といった一定の交通違反歴がある高齢運転者は、事故発生率が高い傾向にあることが問題視されるようになりました。
このような実態を受けて、次なる制度改革として、運転技能そのものに着目した新たな検査制度の導入が検討されることとなります。
こうして、後の「運転技能検査」制度へとつながる流れが形作られていくのです。
6.2022年|運転技能検査の導入と制度の再編成
2022年、75歳以上の高齢ドライバーに向けた制度に、大きな見直しが入りました。
これまでの「認知機能検査」に加え、新たに**「運転技能検査」**が導入されるなど、制度はさらに高度化・実効性の高いものへと進化しています。
① 運転技能検査制度の導入
新たに加わった「運転技能検査(技能検)」は、過去3年間に一定の違反歴がある75歳以上のドライバーに対し実施される、いわば“実地版の適性試験”です。
▷ 対象となる違反例(直近3年間)
- 信号無視
- 一時停止無視
- 通行区分違反
- 指定場所一時不停止
- 進行禁止違反
- 安全運転義務違反 など
これらの違反歴がある方は、運転免許更新時に技能検査を受けなければなりません。
合格しなければ、免許更新はできず、運転ができなくなります。
▷ 検査内容
- 指定されたコースを運転し、
- 安全確認・右左折・停止・発進などの動作を
- 教習所レベルの基準で評価します。
② 認知機能検査の基準変更・デジタル化
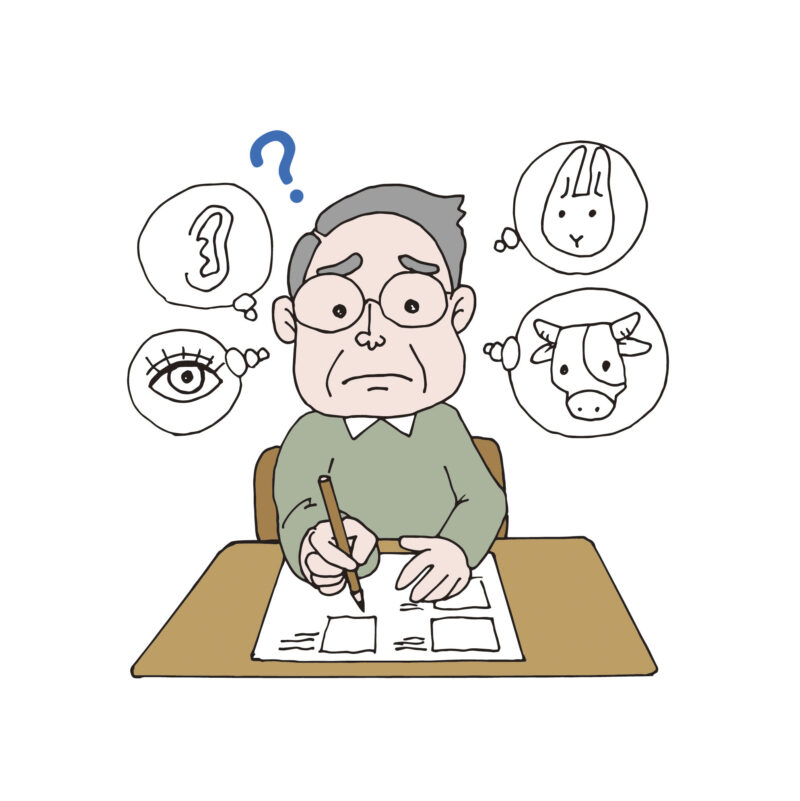
一方、これまで実施されていた「認知機能検査」も、大幅な見直しが行われました。
▷ 判定区分の変更(3区分 → 2区分)
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 区分Ⅰ:認知症のおそれなし | 認知症のおそれなし |
| 区分Ⅱ:低下のおそれあり | 認知症のおそれあり |
| 区分Ⅲ:認知症のおそれあり | 〃 |
⇒ シンプルな2分類に統合され、より分かりやすい制度に。
▷ 「認知症のおそれあり」の基準点数が変更
| 時期 | 判定基準 |
|---|---|
| 改正前 | 49点未満 → 「認知症のおそれあり」 |
| 改正後 | 36点未満 → 「認知症のおそれあり」 |
点数のハードルが下がったことで、本当にリスクのある層の抽出精度が向上しました。
▷ タブレット端末による検査が可能に
- 手書き方式だけでなく、タブレットによる受検が可能に。
- 検査の効率化・採点の正確性アップ・操作の簡便化など、多くのメリットがあります。
制度の進化を年表でおさらい!
| 年 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 1997年 | 75歳以上に高齢者講習を義務化 |
| 2001年 | 対象年齢を70歳以上に引き下げ |
| 2009年 | 認知機能検査を導入(75歳以上) |
| 2017年 | 検査結果に応じた講習振り分け(2時間/3時間)制度導入 |
| 2022年 | 技能検査の導入・認知機能検査の基準見直し・デジタル化 |
まとめ
高齢者講習制度は、交通事故の抑止と高齢者の運転継続のバランスを保つため、時代とともに進化してきました。最初は任意だった講習も、事故や高齢化社会の進展とともに義務化・高度化され、今では運転技能検査や認知機能検査など、科学的な根拠に基づく精緻な制度へと変貌を遂げています。
一方で、高齢者講習の受講枠や運用体制の整備、教習所への負担など、現場には依然として課題も残っています。これからも、高齢ドライバーが安全にハンドルを握れるよう、制度の改善が継続されることが求められます。



